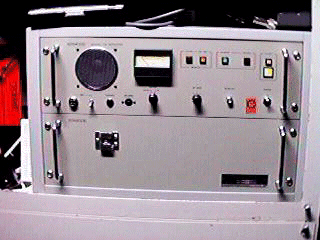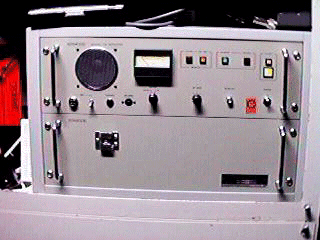JR9VQの設備
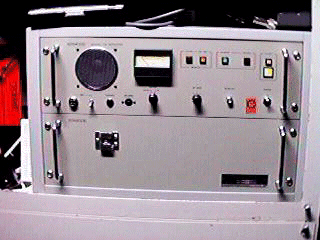
JR9VQのご本尊(?)全国へ電波を届ける
- 設備概要
- 本体の設備費はわずか5パーセント。かかった工事費の大部分は落雷対策という厳重さ。開局以来すでに
年を過ぎてかなりの大きな落雷は何度もありましたがまだ大事故はありません。
- 機器構成
- 本体 ケンウッド TKR-200A
- デュプレクサ アンテン GDU-733
- 蓄電池 アルカリベント型 200AH
- 同 鉛 触媒式 100AHx6台
- アンテナ アンテン 400C-D13VN
- 主要諸元
- 送信周波数 439.12MHz
受信周波数 434.12MHz
受信トーン周波数 88.5Hz
定格送信出力 10W
実効放射電力 76W(理論値)
空中線海抜高 3,003m
限界サービスエリア 357Km(あくまで理論値半径)
- 設計思想
-
- そもそもレピーター局は電波状態の悪い区間を補うための無線中継設備です。従って、設置される場所は環境がいいところなどあり得ません。しかも、アマチュア無線のレピーター局は連盟直轄局を除きボランティアによってのみ運営され、公的機関や業務用のように無制限にいくらでもお金を使い放題にできるわけでもありません。
また、そのような業務としての1対1の通話ならば、今や携帯電話で済ませる方が現実的です。
また、そう言う設置条件のいいところでは携帯電話網が完備されつつありますし、大量生産の端末は安く簡単に入手でき免許すら必要ありません。
しかし残念ながら、レピーターとはこういった悪条件下で運用されることを機器メーカーは理解できず、地上の電源事情のいいところでの設置を前提とした大量生産をしている現状です。設置場所の悪条件など考慮できるアナログ技術者もどんどんいなくなったのと相まって「地上での安定な電源を使い放題」を前提としているため消費電力が大きくしかも電源電圧などの変動に対応できないのが既製品です。最近のデジタル機はもっと凄い電力を消費します。これはさらに電源やその他の条件のいい地上での場所への設置しか考えておらず、本来の「電波を中継をする」というレピーター局のあり方を外れ「電波は接続手段」という携帯電話の考え方となりました。これはもうレピーター局ではなく携帯電話基地局そのものです。
JR9VQはアマチュア無線本来の考え方を遵守・尊重して既製品のレピーター機器の状態や形体を保持したまま、待機電力を通常の1/10に押さえて北アルプス3000m山頂という最悪の自然環境の中で中継局として無線の可能性の極限を追求しているのです。
- JR9VQはアナログ技術の集大成 (落雷対策が95%)
- いまや世の中はデジタル万能世界に突入しています。しかし、最新の宇宙技術を支えるのが町工場の手作業であるように、すべての電気回路の基礎はアナログです。0と1だけで片付けられません。
0はゼロでも1は何ボルト、何アンペアという値があります。この値を無視してはデジタル技術はあり得ません。先日若い技術者がマイクロチップ社のPIC出力をいきなり車両用のモーターにつないで「まわらないなぁ〜」と悩んでいたという笑い話のようなのを聞いてそんな時代になってしまったのかと嘆かわしいことでした。
さて、ご存じの通り、山頂付近はガラスのような電気を通さない花崗岩ばかりです。接地抵抗を簡単に下げることは不可能ですが、JR9VQは雷雲の真っ只中というこれだけ過酷な環境の中で当初「一シーズンなんて絶対に保たない」と囁かれていました。それなのに、
年もの長い間スズメバチの巣を突っついた以上に回りじゅうから鉄板をも溶かすような激しい落雷攻撃を受けながら一度も大きな事故がないのはアースの技術そのものによるものです。すなわち集大成されたアナログ技術を実証している(基本に忠実に配線している)ということです。
真空管のアナログ回路はインピーダンスが高いのでノイズに悩まされた方も多いと思いますが、落雷は超大きなノイズそのものです。コモンモードノイズよりもノーマルモードのノイズの方が被害が大きいですが、山頂ではこれらをプリント基板上で論ずるようなわけにはいきません。それは、アースはつなぎ方で循環電流が起こるからです。でも基本通りにさえしていればすべて解決します。もうおわかりだと思いますので、あとはご想像にお任せします。
最近の、太陽光パネルメーカーでも残念ながらアナログ理論のわかる技術者はいらっしやらないようで「えーっ、こんなアースの取り方をしたら必ず壊れるでしょ」という配線方法を推奨しておられ、「それ以外は保証外」なんて「これがトップメーカーのすること?」と目を疑うばかりです。
年の実績とノウハウを蓄積してきた私たちから見れば情けないことです。ソーラーパネルの業界はまだ歴史も浅く私たちのようなアナログのノウハウの蓄積はないのでしょうね。
JR9VQは北アルプス3000m山頂という最悪の自然環境の中で、より確実に事故をなくするためのアナログ技術をも追求しているのです。
戻る